●通夜・葬儀の日程は葬儀の主要参列者の到着時間、僧侶の都合、火葬場の都合、斎場の空き具合を調整しながら決めるので、葬儀社係員に調整を委ねながら進めていく方が望ましい
- 遠方の親族や主要な参列者の到着時間を申し出る
- 死後24時間は火葬をすることが出来ない
- 葬儀は友引を避けることが多い
|
●葬儀内容を決定する
- 故人の遺志があれば、まず伝える
- 宗旨・宗派、菩提寺を伝える
|
●葬儀料金については、セット料金で提示される場合と、一つひとつの品物やサービスの料金を積みあげて提示される場合がある
- あらかじめ希望価格があれば、ハッキリと伝える
- 葬儀料金がどの範囲まで含まれているかを明確に聞いておく
(不明瞭な部分をなくし、後日問題が起こらないようにしておく)
|
|
 |
| ●葬儀に必要な祭壇・葬具、会葬礼状、粗供養品などを注文する |
|
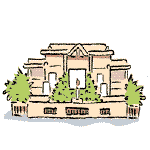 |
| ●喪主、親族は喪服を準備する |
| ●看護滞在中に亡くなられた方々や出張先から直接来られた方々のために貸衣裳が必要になることもある。 |
●斎場では貸衣裳を用意しているので、とりまとめて注文する
(通夜にご入用の方は、その旨を申し出る) |
|
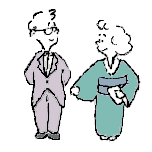 |
| ●斎場では、一般的に仮眠施設を提供していることが多い |
| ●遠方から来られた方で、いったん引き取られる方のためにホテル等を用意する |
|
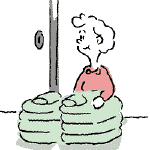 |
| ●親戚間で、供えるものを相談する (「子供一同」「兄弟一同」「親戚一同」として出される場合は、それぞれの 方に了解を得る) |
| ●親戚関係についての集金する人を決めておく |
| ●親戚から取り次いだものは、集金方法を確認する (葬儀社から直接請求してもらう場合は申し出る) |
|
●注文に際してはとりまとめ責任者を決め、一括して申し込む
- 葬儀社で用意した注文書を利用すると便利
- 肩書き・氏名を書き間違えないよう注意する
|
|
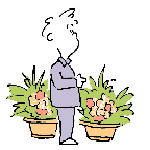 |
| ●精進落しを依頼する親戚の範囲、来賓を決める |
|
●出席を依頼する方々に声をかけ、人数をまとめる
- 料理は出席者人数でまとめる
- 引出物数は家族の数でまとめる
- 僧侶の料理、引出物も人数分に加える
|
| ●料理の申込締め切り時間までに、数量を連絡する |
|
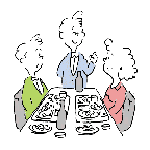 |
| ●火葬場まで同行を依頼する親戚の範囲、来賓を決める |
| ●同行を依頼する方々に声をかけ、人数をまとめる |
| ●葬儀社担当者に人数を伝え、ハイヤー、タクシーまたはマイクロバスの手配を葬儀社に依頼する |
|
 |
Copyright (C) 1996 SEKISE, Inc. |